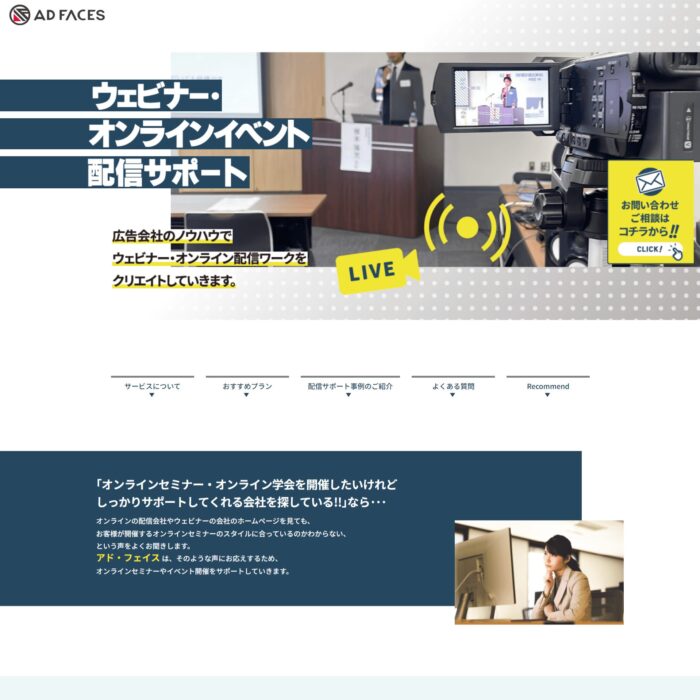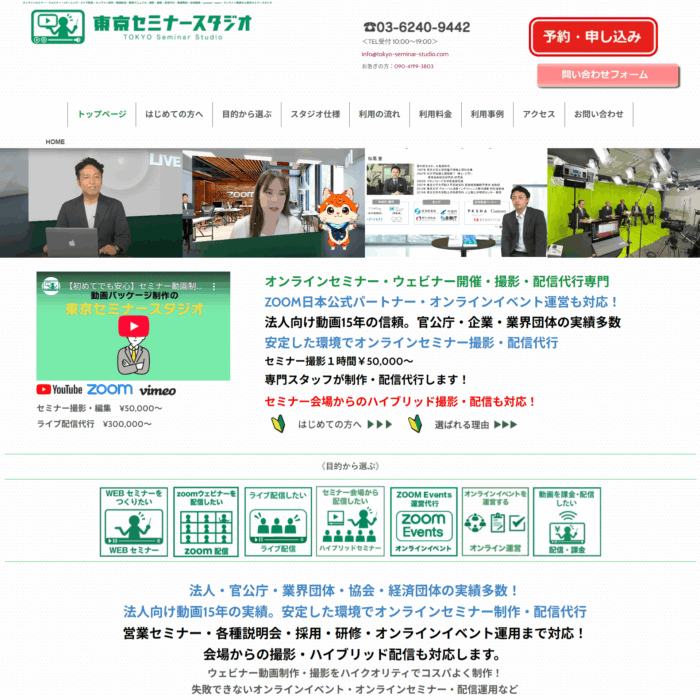コロナ禍をきっかけに、オンラインのコミュニケーションが増えました。ビジネス上でも急激に普及し、利便性を実感しているでしょう。中でも、企業から顧客に対するアプローチとしてウェビナーが注目されています。多くのメリットがあるので、ウェビナーについて理解しましょう。ここでは、ウェビナーの意味やメリットについて解説しています。
ウェビナーとは
ウェビナーは、WEBセミナーの略です。オンラインセミナーと呼ぶこともあるでしょう。ここでは、ウェビナーが注目されている理由や活用方法を紹介します。注目される理由
新型コロナウイルスの影響で、多くの対人イベント・セミナー・研修などが中止になりました。企業にとって、集客や営業が困難になり致命的です。そこで、経営危機を乗り越えるために、あらゆる業界がウェビナーを活用しました。ウェビナーの展示会・イベント・セミナーであれば、対人を防ぎ問題なく業務が進みます。顧客に対するアプローチの機会を奪いません。そして、業務効率がよくなることも含め、企業からウェビナーが注目されました。対人で行うべき業務を見直し、臨機応変に活用する企業が増えています。
活用方法
これまで会場を準備して行っていたイベントや展示会をWEB上で行います。主催者がウェビナーツールを使い、参加者募集や招待が可能です。顧客へのアプローチだけではなく、採用活動や社員教育にも応用できます。画面越しに動画や画像の共有が可能です。ウェビナーツールによって参加上限は異なりますが、Zoomであれば1万人まで参加できます。
主催者は会場設置の手間がかからず、参加者も移動時間がかからないため効率的です。上手な活用をすることで、興味や好感を抱くチャンスとなるでしょう。
ウェビナーとWEBミーティングの違い
企業内・部署内で、WEBミーティングを行うことは多いでしょう。ウェビナーと同じく、WEB上で動画や画像共有が可能です。異なる点としては、WEBミーティングは画面越しに対話を行います。資料を見ながら、リアルタイムに意見交換することが目的です。しかし、ウェビナーは、主催者と参加者に分かれています。基本的に参加者は発言できないシステムです。しかし、主催者が参加者を指定することで、発言ができるようになります。そのため、質疑応答の時間を作ると参加者は満足できるでしょう。一方的な配信のため、会社説明会・研修などに向いています。
ウェビナーを利用するメリット
さまざまな業界でウェビナーを利用する価値があります。売上や利益に関わるので、企業の将来性を支えるでしょう。ここでは、ウェビナーのメリットについて解説します。大勢に対する配信
1度のイベント開催で、世界中に情報配信が可能です。そのため、大勢が同じ情報を得られます。何回も同じ内容を発信する必要がなく、スケジュールに余裕ができるでしょう。効率的な伝達力がメリットです。経費削減
イベントを開催するには、多くの経費が必要です。会場レンタル費・設営費・交通費・人件費など、参加人数が増えるほど高くなります。経費をかけたうえでメリットが得られなければ、イベントは失敗に終わるでしょう。しかし、ウェビナーであれば経費がかかりません。また、会場予約などの手間がかからないので、気軽にイベントを開催できます。
業務簡略化できる
イベントを開催するには、多くの業務が発生します。当日であれば、会場準備・受付・案内などがあるでしょう。主催者からスタッフに流れを共有、指示するにも手間がかかります。また、終了後の片付けも必要です。さらに、自社の従業員を動員する場合、コア業務から離れることになります。それぞれの部署で人員が減るため、業務にも支障がでるでしょう。
しかし、ウェビナーであれば、業務簡略化が可能です。イベントスケジュールの告知や、資料作成など最低限で済みます。
参加者に制限がない
参加者が世界中どこにいても、情報共有できることがメリットです。従来の対人イベントの場合、参加までに時間と交通費がかかります。そのため、遠方からは参加しにくい環境でした。しかし、ウェビナーであれば、参加者に負担がありません。移動の手間や交通費をかけさせないため、時間を作ってもらいやすいでしょう。新規顧客開拓や採用活動に貢献します。
ウェビナーを利用するデメリット
多くのメリットが存在するウェビナーですが、デメリットもあります。メリット・デメリットを精査したうえで、導入すべきか判断しましょう。ここでは、デメリットを解説します。参加者の集中力が切れる
ウェビナーは、主催者がほぼ一方的に情報発信を行います。また、主催者からは顔が見えないため、参加者の聞くスタンスは自由です。ほかのことを行いながら、聞く可能性もあるでしょう。そして、集中力が切れて、離脱することも多くあります。主催者は、興味を引く内容や話し方が必要です。
通信環境によるトラブル
ネットを使うという特性上、通信環境によるトラブルを想定しましょう。動画や音声の不具合が発生した場合、何も伝えることができません。また、主催者側の通信環境だけではなく、参加者側の通信環境も影響します。そのため、確実な対処方法がないことがデメリットです。